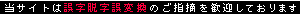望みの果ては 12話
‐
いつもの深夜徘徊。
いつものごとく、左にはヒバリがいて。いつものごとくある程度やって、空の暗闇がほんの少し薄くなったらそれぞれの家に帰るはずだったのだけれど。
なぜかツナたちの目の前にいるのは、昼間のツナの命の恩人。
「いやーおまえが夜の街にいるなんて思いもしなかったぜ。案外ませてんのか?」
「いや・・・その」
彼の名前はシャマル。
優秀な医師、そして殺し屋という職業からDr.シャマルとも、トライデント・シャマルとも呼ばれている男だ。
なんでも333対の不治の病をその身に宿らせながらも、互いに相殺しあわせることにより健康体を保っているらしい。
ツナはシャマルに昼間、死ぬ気弾というボンゴレの特殊弾による副作用で発病した不治の病、ドクロ病を治してもらっていた。
そのシャマルの横にはいかにもな露出の多い女が甘えたように腕をくんでいる。
ツナがどういう言い訳をしようかと頭をフル回転させていると、シャマルがツナの横に立っていたヒバリを見た。
「おまえさんは?」
「綱吉、これ何」
「あー、またこいつのファミリーか?」
「関係ありませんから!」
シャマルはヒバリを指差して言った。
ヒバリは険しい顔をして、頭上にハテナマークを浮かべていた。
当然だ、ヒバリは一切マフィアのことは知らないし、関係もしていない。
ボンゴレやらマフィアやらの単語を出される前に早くこの場を去らなければ。
シャマルと腕を組んでいる女が、すっとヒバリに手を伸ばす。
「あら・・・こちらいい男じゃない。もちろんアナタには負けるけどぉ・・・」
「触らないでくれる」
「ばっ、駄目ですって!」
女の手がヒバリの頬へと届く前に、ヒバリは身を引いてトンファーを突き出す。
ツナがその一瞬の間に女の前に立つと、トンファーは女の顔面寸前でとまった。
女は顔を青くし、シャマルの後ろに引っ込んだ。
「ひっ・・・! なによこれ!」
「おいおい、レディに手ェあげちゃいけねーぜ」
シャマルが呆れたように手を広げた。
生粋のイタリア人らしく、彼はものすごいフェミニスト・・・というか極度の女好きであったため、女を邪険に扱うヒバリが理解できないのだろう。
かといって、彼のことは日本人でも中々理解しづらいと思う。
ヒバリに触れようとした女は、独特の風俗的な雰囲気をもってはいるが、顔は平均よりずっと整っており、胸も大きく腰も細いというボディバランスは完璧だ。
妖艶という言葉が良くにあい、日本の一般男子でも話しかけられたり、ましてや触れられようとするものなら、振り払ったりはしないだろう。むしろ嬉々とするだろう。
ヒバリの行動を完全に把握できるものなど居やしないのだ。
「す、すみません! えと、これで失礼します・・・・っほら、行きましょう!」
「ちょっと、綱吉?」
女に深々と礼をした後、ボロを出してしまう前にさっさと引いてしまおうと、ツナはヒバリの背を押し押し、シャマルと女から遠ざかろうとする。
ところがそれはむなしくも、シャマルによって止められる。
「ちょっと待て、おまえまだ足痛ェんだろーがボンゴレ坊主。さっさと家帰って安静にしてろ」
「は、はい、そーですね・・・・」
この男・・・ボンゴレって口にしやがった!!
オレが頑張って今までそういう単語を、恭弥さんに聞かせないように頑張ってきたのに!
細かいことはあまり気にしないおおらかな奈々と違って、ヒバリは一単語一単語への注目が鋭い。
いくつかのヒントからすぐに結論を出せるぐらい、頭の回転もすぐれている。
だからこそツナは注意を払ってきたというのに、軽々と漏らしやがった。
「じゃ、安静にするため家にかえるんで。失礼しましたっ」
地味に痛む足でヒバリを引っ張りつつ、今度こそ全力でその場を後にした。
シャマルには昼間、ドクロ病のことで一悶着あったときに、足を痛めていることを見抜かれていたのだ。
まあ、彼の信念により治療はしてくれなかったが。
-
二人は人通りのほとんど無い店先に来た。
ツナはずいと、ヒバリにつめよられる。
「ねえ綱吉。あの男なに?」
「・・・・あえて言うなら恩人です?医者なんで」
「誰の、何の」
「オレの、命の」
ヒバリはふっと視線をそらして、また戻す。ほとんど光の宿っていない、闇色の瞳に捕らえられて、目がそらせない。
というか、ヒバリの手によって顔固定されているから動かせないだけなのだが。
なんか顔が近い気がする。
「ボンゴレってなに」
「あの人イタリア人で、イタリア語・・・・直訳すると二枚貝ですね、あさりとか」
「なんで綱吉がボンゴレって呼ばれてるのか聞いてるんだけど」
「さ、さぁ?」
「黙秘するのかい?」
「あなたに教える必要感じませんから」
冗談じゃない、言ってなんてやるもんか。
ツナが大きなマフィアの10代目(本人になる気は一切ないが)だと知れば、ヒバリはさも面白そうに首を突っ込んで来ることは間違いない。
そうすれば、一般人どころかそこらの殺し屋より強固な戦闘能力を持つ彼を、リボーンはファミリーにしようとするだろう。
因みにこのあたりに当事者であるツナの意見が取り入れられることはない。
話を戻すが、ヒバリがファミリーに入ってしまえば、自称ツナの右腕な彼が突っ掛かっていかないはずはないし、なによりこの好戦的な男がまじって問題を起こさないはずがないのだ。
ツナのまわりが騒がしくなるのは想像の段階でも100パーセントの保証がくる。だから言わない。
ヒバリはトンファーをかまえたが、この手の脅しにツナが口を開いたことがないのを思い出してか、静かにそれをしまった。
その間も二人の視線は絡み合ったままだ。
「・・・なんで足怪我してること言わなかったの」
「怪我っていってもほとんど痛まない程度なんですよ」
一応包帯を巻いているとはいっても、ズボンでその部分は完全に隠れている。
学校にいたとき、ツナは周りに感づかれるような歩き方をしていたつもりはない、逆に隠し通せるよう自然に歩いていた。それで気づいたのだから、シャマルの医者としての腕は確かだと認めざるをえないのだろう。
シャマルが一端の医者であるから気づいたのであって、ヒバリがツナの足の怪我に気づかないのはあたりまえなのだ。
ヒバリがじっとツナの怪我をしている左足を見ている。
醸しだす空気が、いつもより重い。
「・・・・・・帰るよ。送る」
「え、なんでですか? 別にいいですけど。必要ないし」
ツナが平然とした顔でそう言うと、ヒバリはツナの後頭部をつかんでツナの家がある方へひっぱり始めた。痛くはない。
文句のひとつでも言いたいところだったが、ツナが望んだわけではないとはいえ送ってもらっている以上、失礼だと思いそれは喉奥へと飲み込んだ。
「ほんとに大丈夫です。少しは走ったり跳ねたりも出来ますし、そりゃ患部に触れば痛みますけど」
ツナが伺うようにそう言っても、ヒバリがなにか反応することはなかった。
そのままお互い無言でツナの家まで歩いた。
そこでも他人行儀のような会話を交わして、ツナは家の中に、ヒバリは再び夜の街に消えていった。
もう夜が明けるというのに、どこに行くんだ、あの人は。
-
イライラする。
自分が気がつかなかったことに。
それをそこらへんに居そうな中年がやすやすと見抜いた(実際は医者の上にプロの殺し屋なのだから当然といえば当然だが)ことに。
隠していた淡い茶の髪と瞳を持つ彼にも。
何故こうもイライラするのかさえわからない。
そういえば昔から、人一倍執着心は強かった気がする。欲しいものは必ず側に置いた。どんなものであっても。それが当然だった。
今だって側に置いてるじゃないか。何が不満なんだ僕は。
何をイライラしているのかわからなくて、それがまたイライラを募らせる。
ヒバリはふぅ、とらしくもないため息を吐いた。
・・・・・面倒だな。こういうときは咬み殺すに限る。
そう思考し終えた直後、正面から歩いてきた集団の一人と、ヒバリの肩がぶつかった。
ぶつかった男が、ヒバリに対して怒鳴りつけてくる。
「てめぇぶつかっといて何のワビもなしか!? おいこら、聞いてんのか!」
「なに、僕にたいして言ってるの」
「は? てめー以外に誰がいんだっつの!」
「っオイ、こいつヒバリじゃあ・・・・!」
男は、ヒバリの着る学ランと風紀の紋章に気がついたようだったが、遅かった。
集団全てを地に伏させたあとも、わずかに残るわだかまりを彼は無理やり無視した。
09.09.12